番外編 〜危険生物対処法〜
2014年9月。ついにマムシに咬まれてしまいました・・・
数年前に調べまくった知識が頭に残っていたため、不幸中の幸い・・・軽く済みました。
これを機に、自然界に存在する危険な生き物への対処方法を記録に残します。
ここでは特に死亡例の多い、毒のある生き物、鋭い武器を持った生き物などを中心に載せて行きます。
※私は専門家でもなければ医師でもありません・・・ネットを検索して有効と思われるものを取捨選択して紹介しています。
※私の住む地域周辺で生息していない生物は除外してあります。
南方系・・・ハブ、ヒョウモンダコ、ハブクラゲ
北方系・・・
※調べるのに時間が掛かるので、少しずつ増やしていきます。
<< マムシ咬傷 >>

ニホンマムシ。
写真は、私の左手人差し指に喰らい付いた・・・史上最強のマムシくん。

動画はスロー再生です。
とても攻撃的な子持ちのマムシ・・・これにやられて処置が悪いと1ヶ月以上の入院〜最悪、命を落としてしまいます・・・

マムシのキバ。長さ5mmほど。
細くて中は空洞・・・とても脆く、取れやすいです。
毒液を注入するための穴は先端付近にとても長く大きく開いてました。
まるで注射器ですね・・・
もし咬まれてしまった場合の対処方法をネットで検索すると・・・真逆の対処法も沢山ヒットします・・・
もし何も分からなければ、とにかく安静を保って一刻も早く病院へ行くこと・・・これも最善の方法の一つなのです。
1、口で毒を吸い出す・・・口腔内に傷などがある場合は不可です。また、当然ですが、口が届かない箇所は・・・他人(家族)にお願い
するか、ポイズンリムーバーなどを使用します。
この処置は賛否両論ですが、多少のリスクはあっても一刻も早く毒を体外へ出してしまう方が軽症で済みます。
私の場合、咬まれた直後に虫歯や口内炎がなかったか思い出してから吸出しを試みました。
切開して毒を絞りだすとの情報もありますが、毒の回りを早めてしまったり、怪我を酷くする、さらに破傷風などの感染症の危険もあるの
で止めたほうが良いです。
2、とにかく慌てないこと・・・走って心拍数があがると毒の周りも早くなります。毒の回りを抑えるためにも安静にすること。ただし、
一分でも早く病院に受
診する事も重要です。咬まれてから30分程度で目が見え難くなったり、意識が朦朧とする事もあるので、それを目安に下山などの行動計
画を直ぐに立てる事。
私の場合、近くの病院が何処なのか、また、住所も分からなかったので、歩いて車に戻り、近くの民家まで自分の体調に注意を払いながら
車で移動しました。
3、縛る・・・傷口よりも心臓に近い部分を縛ります。これも毒の回りを抑えるためにするのです。あまりにも強く縛りすぎても逆効果で
縛った先が壊死してしまいます・・・
定期的に解いてやるとか、素人には難しいので縛らない方が良いとの情報もあります。
私の場合、気休め程度に、軽く圧が掛かるほどに縛りました。
4、冷やす・・・意識が飛びそうなほどに痛みが酷い時は冷やす事で痛みが和らぐ(感覚が鈍くなる)ようですが、悪化させてしまうので
可能であればやらないほうが良い。
私の場合は、我慢できる範囲だったので冷やしませんでした。
5、病院で治療する・・・仮に症状が軽いと思われても、時間とともに毒が体にまわり、ショック症状が現れたり、破傷風などの感染症の
危険もあります。
必ず受診する事をおすすめします。
私の場合・・・記憶を辿るとこんな感じ。
8:50頃・・・左手人差し指にハチに刺された様な強い痛みが走る。
近くにマムシを発見し、直ぐにマムシに咬まれたことが判明。
キバは1本しか刺さらなかったようで、穴は一つ。
みるみる紫色に変色していきました。
毒の吸出しを何度も試みながら、歩いて車まで移動。
9:00頃・・・車に到着。運転しながら、毒の吸出し、自分の意識の確認。
9:10頃・・・近くの民家に着くが、畑仕事か・・・玄関は開いていても誰も居ない・・・
3度目にお婆さんを発見し、マムシに咬まれたことを告げる。
一番近い病院を訪ねるが、場所が分からないうえに、遠いようなので
救急車を呼ぶ。お婆さんに聞いた住所などを伝える。
救急車が来るまで大分待ちました・・・この間は、椅子に座りながら、
軽く指の付け根を縛りました。
9:40頃・・・やっと救急車が到着。心拍・血圧などのチェック、簡単な問診など・・・
この時、人差し指全体が腫れ、手のひら部分へも少しずつ広がりだした
感じでした。
問診が終わったら、救急隊が近くの病院へ受け入れ要請&確認。
山の中なのでふもとまで降りていてくれれば・・・と何度も思いました・・・
9:50過ぎ・・・救急隊は、受け入れ確認が取れてから車を発進させました。
10:00過ぎ・・・病院へ到着。
直ぐに大量の点滴投与・・・毒を薄めて体外へ排出させるのが目的。
麻酔を打って毒の絞り出し・・・散々吸った後なので効果あったのか・・・・
破傷風の予防注射も打ちました。
入院決定で、血液検査、心電図、レントゲン撮影などなど・・・
点滴・モニター(心拍数などがわかる)を付けっぱなしで、
ナースステーションのすぐ横(緊急時にすぐ対応するため)の部屋へ。
夕方・・・左手の手首から先は手袋でもしてるようにパンパン。
ヒジ部分に腫れと痛み、左胸の一部にも痛みが来ました。
先生と相談し、ここでマムシの血清を打ちました。
症状が軽ければ血清を打たない事が多いです・・・何より、咬まれた
本人が本当にマムシだったか判断できない場合も多い・・・
血清を打つことにより、ショック状態(アナフィラキシーショック)になって
しまう事もあるためです。
頓服で痛み止めをもらいましたが、10割の痛みが8割になる程度でした。
夜間・・・痛み止めに座薬を入れてもらいましたが、やはり痛い・・・
何時でも何処でも寝れる性格もあってか、痛くても朝5:30頃まで眠りました。
翌朝・・・痛み止めが切れだすとやはり我慢しずらい痛みでした。
指に血液が溜まっていたので切開して出しました。
3日間入院と告げられたのですが、交渉して血液検査の結果が良ければ
退院してよいと、先生から確約を得ることが出来、昼には無事退院できました。
1週間分の抗生剤(飲み薬)をもらって飲み切り、10日後に外来予約。
10日後・・・外来受診して回復も順調。こちらも交渉して外来も終了になりました。
第一関節より先はかなり腫れてますが、それ以外は元に戻りました。
抗生剤(塗り薬)をもらい、自分で手当てしていきます。
内部から組織が壊されたので、完全に回復するには相当な時間が掛かり
そうです。

咬まれてから15日後です。
途中、ずっと包帯をしていたからか、血の気がなく真っ白!! このまま腐って落ちるのか!?と、思いました。
予防法は、草むらに近づかない・・・は当然ですね・・・
ヤブに入るときはゴム長靴を必ず履くようにしましょう。地域にもよりますが、体長はせいぜい50〜60cm程度です。長靴で十分防げ
ます。
ヤブに手を入れるとき(山菜採りなど)は、あらかじめ棒などでガサガサ払う、良く確認するなどしましょう。
居そうな気がする場所では、ドシドシ地面を踏みしめながら歩くと、マムシは早めに気付いて早々に立ち去ってくれます。「窮鼠却って猫
を噛む」・・・マムシが逃げるタイミングを失ってしまうと、その場にジッとし、さらに近づくと攻撃してきます。
<< ヤマカガシ咬傷 >>
マムシと異なり、人と出会うと逃げるタイミングを見計らってアッと言う間にスルスルと何処かへ行ってしまいます。

毒牙は一番奥にあります。

左右2本ずつありました。
毒が通る穴など何処にもありません・・・
正確には毒牙ではなく、この牙で刺した傷から毒が入るのです。
ヤマカガシ。
対処方法は、マムシと同じです。
マムシとの違いは、
比較的大人しいヘビです。毒牙はありませんが、奥歯でかまれた場合、毒腺から出てきた毒が傷口から入ってしまいます。浅くかまれた場
合は大丈夫。
ただし、毒性の強さからすると、ハブやマムシよりもずっと強力なのです。
咬まれてから10〜30分程度では、軽い頭痛や腫脹程度、4〜30時間後に全身の出血症状が現れる・・・ハッキリとした症状が出るま
でかなり時間があるので、安易に判断してしまいがちになると思われます。
奥歯まで完全に咬まれてしまった場合は、念のため、病院へ受診する事をすすめます。
その他、ヤマカガシは頚部より別の種類の毒を出す場合があります。
目に入った場合、最悪の場合は失明の恐れがあります。直ぐに流水で洗い流し、症状により病院へ行きましょう。
予防法は、ヤマカガシに触らないこと。
他のヘビ同様に、臆病な性格です。人の気配を察知すると、逃げるタイミングを計ってスルスルとあっと言う間に居なくなってしまいま
す。
手で持って遊んだりしなければ、襲い掛かってくる事はまずありません。
<< マダニ症 >>

ダニが皮膚に食い込んでいる所。
刺されても何も感じない事が多いのですが、この時はとても痒かったです・・・
まだお腹がペッタンコなので、吸い始める前です。
ダニを除去した後、数日間腫れました。
またまた別の場所・・・
血を吸って大きくなる前は小さいので、お風呂で汗を流しながら体の隅々までチェックしましょう・・・
このときもダニは上手に除去できたのですが、大きな水泡になり痒かった!
ピンセットで摘んでゆっくり引き抜いたもの。
肉眼でもこの形は確認する事ができます。一部が取れていたら、まだ皮膚の中に残っていると言う事・・・

何処にでもペタペタと引っ付く感じで歩ける・・・その脚を超拡大したら・・・脚の先端に自由に動く鉤爪がありました。
山やヤブに入った当日は、お風呂でシッカリ体を洗い、体のあちこちを入念に確認(目で見る、見えない所は手で確認する)などしましょ
う。
体の柔らかい部分に咬み付きます・・・特に股間は見落としがちなので丁寧に・・・私は8月1ヶ月間だけで3匹も・・・ち○ち○
に・・・私の場合、ここが一番重要チェック箇所です。ここを咬まれると腫れや痒みが半端無い・・・
もし刺しているのを見つけたら・・・
1、ピンセットで皮膚に一番近い部分を摘んでから、真っ直ぐゆっくりと引き抜きます。
もし皮膚の中に残ってしまい、取り除くことが出来ない場合は病院へ行きましょう。
刺してから24時間以内に除去できれば、感染率を抑えることができると言われています。また、咬み付いてから24時間経つとセメ
ントの様なもので強固に固定されてしまうのでさらに取り除き難くなってしまいます。
熱(焼いた針金)やお酒などで取れる場合もあるようですが、私は何度か熱で試してみましたが、取れたことはありませんでした。ま
た、マダニに咬まれているヘビをそのままお酒に漬けた事もありますが、取れませんでした。
2、無事に除去することが出来たら良く消毒して下さい。
当日無事に見えても、感染症の症状は数日後から現れる事が多いです。
マダニ感染症には、様々なものが存在します。
以下は主なもの。
○重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)
6日〜2週間程度で、原因不明の発熱、消化器症状(食欲低下、嘔気、嘔吐、下
痢、腹痛)が中心です。
重症化し、死亡することもあります。
○日本紅斑熱・つつが虫病
日本紅斑熱は2〜8日後に高熱、発疹、刺し口(ダニに刺された部分は赤く腫れ、中心部がかさぶたになる)が特徴的な症状です。
咬まれてから2〜8日後に高熱と発しんで発症し、治療が遅れれば重症化や死亡する場合もあります。
真冬を除いてほぼ1年中感染する可能性があります。
○ライム病
1〜3週間後に刺された部分を中心に特徴的な遊走性の紅斑がみられます。また、筋肉痛、関節痛、頭痛、発熱、悪寒、倦怠感などのイ
ンフルエンザ様症状を伴うこともあります。
ライム病は3〜32日の潜伏期間を経て高熱、発疹、全身倦怠感、関節痛が出るのが特徴です。
○マダニ媒介性の回帰熱
12〜16 日程度(平均15 日)に 発熱、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、全身の倦怠感などの風邪のような症状。
予防法は、山やヤブに入らないこと・・・の他、
長靴を履き(ダニが滑りやすい)、ズボンの裾は長靴の中に入れると良いようです。
家に入るときは、服を良く叩いてダニを落とすようにしましょう。
2022年。
実は、2021年、ほんと、山や河原など、どこでも足首程度の草むらでもダニに喰われる!!
ダニ異常発生!? これはヤバイ!!
と言う分けで、2022年はダニ対策で虫よけスプレーを使いました。
効果のある成分はディート。(小さな子供には使えないので、その場合はイカリジンと言う成分のものを使いましょう。)
既に5〜6回使ってますが、一度も喰われていません。効果あります♪
<< ハチ刺症 >>
手が触れるほどに近づいてスズメバチのマクロ撮影・・・周りを数匹のスズメバチが飛んでました・・・刺激を与えないようにゆっくり
ゆ〜っくりと動いて撮影しました。
スズメバチ

針は真っ直ぐではなく湾曲してます・・・
これは実は産卵管が発達したもので、これが直接刺さるわけではありません・・・

超拡大して撮影したら肉眼では全く見えませんが、中に収納されたものがある・・・

奇跡的に素手だけで内部の針を取り出すことに成功しました。
モリの様な構造の針2本を摺り合わせるように刺し込んで毒を注入するのでした。
生き物による死亡者が最も多いのがハチによる被害で、そのほとんどがアナフィラキシーショックです。
ハチには種類(大きさ、毒の強さ)があります。
もっとも強い毒はスズメバチの仲間です。
刺すだけでなく、毒液を飛ばす事もあり、目に入ると失明の危険があります。
その他、ミツバチは一度刺すと針が取れ、刺したハチは死んでしまいます。残った針からは毒液が注入され続けるので、早めに取り除きま
す。
1、まずは安全な場所に避難します。
ハチに刺されると、その場所に興奮物質が空気中にばら撒かれるので、次々に他のハチにも刺される危険があります。
2、毒を体外へ取り除きます。
流水で洗う、傷口の周りを摘んで絞りだす、ポイズンリムーバーを利用する、口で吸い出す(口腔内に傷がある場合は不可)、などを
試みます。
3、病院へ行く。
過去にハチに刺された経験がある場合は特に、アナフィラキシーショックを起こしやすい体質になっています。これは、刺されてから
30分以内に起こる場合が多いので参考にして下さい。

刺された1時間後。ふくらはぎです。
この翌日から2〜3日間、直径10cm近い範囲が、赤くなって少し盛り上がり、肉がカチコチに!!
予防法は、黒い色のものを避けること。
日本人は黒髪が多いですが、黒い色はハチにとって天敵のクマを連想させる色なのです。白い帽子、白い服を着ていればベストですが、そ
んな格好で山歩きなどしていたら・・・それこそ・・・白い目で見られそうです・・・明るい色を選びましょう。
赤い色もモノクロ(白黒)では黒い色になるように濃い色です。唇を刺される事も多いようです。
古くから言われるアンモニア(おしっこ)は、全く効果がありません。
整髪料や香水はハチをおびき寄せます。
身を低くするのは効果があるようです。
1匹のハチを近くで見掛けたら、その動きを良く見ましょう。巣の周りを定期的に巡回している場合があります。決してその巡回範囲内に
入らないように。
その他は・・・運・・・何もしていないのにまっしぐらに飛んできて直撃された情報も多いです。まさに交通事故。起きてしまったら冷静
に対処しましょう・・・
私も子供の頃から何度も刺されています。
虫取りが大好きであちこち行きました。蜂の巣集めなどと言う危険な遊びも・・・
アシナガバチ、トックリバチ、その他小さなハチ・・・などなど。
スズメバチには未だ刺されたことはありません。
<< ムカデ咬創 >>

稀に20cm程にもなります。


キバの先端に僅かな窪み・・・凡そ0.2mm程度。
ここから毒液がでるのかどうか・・・プリンタのインク詰め替え用の注射器に水をいれてキバの内側に差し込み、圧を掛けて見ましたが、
この穴のような部分からは出ませんでした。(方法がダメだった可能性もあります。)
基本的に夜行性ですが、昼間でも雨が降り出した時など、藪の中からウネウネと・・・出てくることがあります。
ムカデに関しては、調べても色々な情報がバラバラと・・・見つかるばかり・・・真実は・・・
毒は、脚が変化した顎肢から注入されるとの情報が一番多い中で、キバ(顎肢)で傷を付けて毒腺から出る毒液を塗り着けるとの情報もあ
りました。
毒を受ける方法にバラつきがあるように、対処方法にもバラつきがあります。
注入された毒はポイズンリムーバーなどで少しでも出した方が良いとの情報や、塗り付けられた毒に対して吸い出したり、揉み出したりす
る事に意味は無いとの情報もありました・・・
また、ムカデに咬まれた時の対処法として、温めるのと冷やすのと・・・両方出てきます・・・
ハチ毒とムカデ毒には共通する成分が多いため、ムカデだけでなく、ハチに刺された事がある場合も、アナフィラキシーショックを起こし
てしまう可能性があります。
色々書いてしまいましたが、全て真実かも知れません・・・
キバから毒液を注入するだけでなく、鋭い足先で皮膚を傷つけ、足周辺からも毒が分泌されるために、毒の塗りつけも行なわれる・・・可
能性があります。
1、皮膚・表面の毒を洗い流す、また、咬まれた場合はポイズンリムーバーなどでの吸出しを試みる。
2、43度以上のお湯に患部を浸す。
それ以下の温度では毒を活性化させてしまうようです。
石鹸水で洗うのも効果的なようです。
3、ステロイド剤を塗る。
この方法は、良く出てくる定番の処置方法。
キンカンに関しては賛否両論。
その他、民間療法としてムカデ油を塗る方法もあります。
4、症状が重ければ、アナフィラキシーショックを疑い、救急車を呼ぶ。
予防方法は、
山がちの場所では、家の中で良く出るようです。忌避剤の利用を検討しましょう。
<< ヤマビル咬傷 >>


山の中の水場へ行ったら・・・尺取り虫のように這っているヤマビルを見つけました。

沢沿いなど、常に日陰で水気のある・・・フキやウワバミソウなどが生える場所・・・こんな所を歩いた時は、時々足元を確認した方が良
いです。
ヤマビルに血を吸われた場合、同じく吸血するダニと同様の危険な感染症に罹る可能性があると思われますが、以外にもネットを検索して
もダニの様に危険性を訴える記事が少ない!!
ただ危険性が無いかと言うと、もちろん、そんな事はありません・・・ヤマビルの体内から各種細菌類が実際に採取されているのです。
予防法は、ダニ同様に皮膚の露出を極力控える事、水辺、湿度の高い場所などに長時間滞在しない事、また意外にもリュックを地面に下ろ
すと、リュックに取り付いて知らずに一緒に背負ってしまうことが多いとか・・・注意している人は、リュックは地面に降ろさず、木の枝
などに吊るすそうです。
ダニ対策に有効なディート成分が入った虫除けスプレーも効果があります。
2024年(サバイバルを始めて14年目)に、初めてヤマビルに出会い、血を吸われました。
この年に2回、血を吸われ、もう1回は車を運転中、ズボンの上を這っているのを見つけました。
上の写真は、2025年、初めて撮影した時の写真です。
(2024年は撮影して記録に残す事を忘れてました・・・)
大きさは3〜4cm程度で、尺取り虫の様に這って移動するだけ・・・そう滅多にやられることはないだろうと思いがちですが、上の写真
を撮った時は、私が先にヤマビルを発見したので、その行動をジックリ観察することが出来ました。
1回の”尺取り”(距離にして2〜3cm程度)は、迷いが無い時はわずか1秒程度、頭を振ってあたりを伺っても2秒程度です・・・あ
る程度ジグザグはしてましたが、まっすぐこちらに向かって這ってきました。
この時の感想・・・もしヤマビルがいる場所の1m以内の範囲に入ってしまったら・・・1分そこに居ただけで取り付かれる可能性は十分
あると思いました。
初めて吸血された時は、家に帰って靴下を脱ごうとしたら真っ赤になっていたので気づきました。
え!? 何が起こった!? 全く痛みを感じない&初めての事だったので頭の中は???でしたが、もちろん、ヒルの事は知って
たのですぐに”これか!!”と分かりました。この時、ヒル自体はすでに居なくなっていたのです。
靴下脱いでそのままお風呂に入り・・・まだ血が出てる・・・乾かせば止まるだろうと、ズボンを巻き上げて、そのまま夕食を摂り終え
て・・・まだ血が止まらない!! ヒルが居なくなっても血が止まらないとは思わなかったのです。
ここで初めてヒルに血を吸われた後の対処法を調べ、再度、風呂で傷口を少し絞るようにしてよく洗ったら、すぐに血は止まったのです。
有名ですが、ヒルは血を吸う際に、血が固まらない成分を出すのですが、その成分はヒルが居なくても体内に残っているようなのです。
<< クラゲ刺症 >>

アカクラゲ。毒性はやや強め。
アカクラゲのの触手拡大。デコボコしてますが、この一つ一つももっと小さなイボイボの集まりでした。
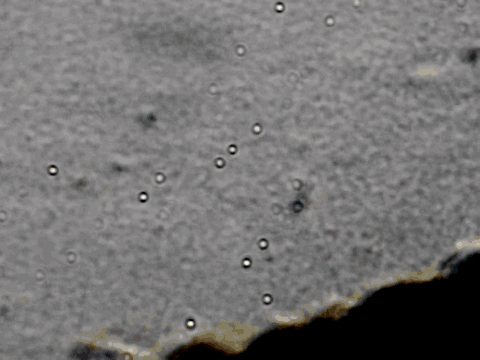
飛び出す刺胞。
揺すってもツツイても飛び出さず、真水を垂らしたら・・・出ませんでした。
お酢ならば・・・大量に出まくり!
ハブクラゲ以外のクラゲに刺された時、お酢を使うと大変な事になります・・・
※少し分かり難い動画ですが、顕微鏡+デジカメの合体撮影、データサイズを抑えるために色数を落としてフレームを省いて圧縮し
て・・・このサイズでこれが限界でした。またいつか、もっと良い動画が撮れたら差し替えるかも!?
カツオノエボシ。
正確にはクラゲではなく、ヒドロ虫の群体です。 これが1匹ではなく、沢山の個体が集まってそれぞれが役割を果たして全体として機能
する素晴らしいシステム・・・それはさておき・・・
クラゲ同様に触手に毒があり、死んでいても機能し、人の死亡例もあるほどの強力な毒です。
クラゲの毒にも種類があります。
刺されると死の危険のあるものから、殆ど痛みを感じない程度のものまで・・・
1、触手の一部が残っている場合は、ピンセットなどを使って丁寧に取り除きます。
素手でさわると、触った手にも刺さってしまいます。
真水を使うと刺激してさらに毒を出してしまいます。
こすらない。タオルやティッシュなどで擦ると毒を擦り込んでしまいます。
2、刺したクラゲがハブクラゲだった場合のみ、酢が効果的です・・・
酢を持って海へ行く人がいるでしょうか・・・
私の住む地域には存在しないので私はパス・・・
クラゲの毒はタンパク毒なので熱に弱い・・・やけどしない程度のお湯を使うと良い
との情報もありますが、実際には60度は必要です・・・やけどしないように注意。
3、病院へ行く。
刺されたのが2度目以降だった場合は、アナフィラキシーショックを起こす場合があります。
自分で、症状を見極めて、息苦しい、鼓動が早いなど・・・危険を感じたら躊躇せず、
救急車を呼びましょう。
予防法は、海へ行かないこと・・・の他、
クラゲを見掛けたら離れること・・・目視しかありません・・・
後は、刺されたら適切に対処することだけでしょう・・・
<< エイ刺症 >>

アカエイ。

尾にあるトゲは、硬い骨の様な素材に薄皮が張り付いてます。

表面の薄皮を取り除いたもの。
体盤幅(横幅)60cmの個体から採取した約10cmの毒針。

流線型で綺麗・・・ですが、刺さったら恐ろしい形です・・・

あちこち見てみましたが、この骨状のものに毒が通る穴などはありませんでした。
この毒針を覆っていた皮の中に毒が通っているのでしょうか。
砂浜に身を潜めているので、間違って踏んでしまうことが多いようです。
砂に埋まって目だけを出す・・・とても気が付き難いです。
海遊び、潮干狩り、釣り(ウェーディング)などの時は注意が必要です。
エイはアサリを食べるので潮干狩りが出来る場所にも居るのです。
河口からある程度淡水域にまで遡上することも良くあるようです。
1、刺された箇所周辺を圧迫し、毒を絞りだす。
エイ自体も大型になるため、針(槍に近い・・・)もとても大きくなります。
靴、足の甲やふくらはぎまでも貫通します。
状況によりその場で判断して下さい。
出血が多い場合は迷わず救急車を呼びましょう・・・
2、タンパク毒のため、40〜45度のお湯に30分以上浸けると良いようです。
出血が多い場合は迷わず救急車を呼びましょう・・・
3、病院へ行く。
槍で足を貫かれる様な感じになるので、傷口も大きく、そのまま病院へ行くことが
多いと思います。
当然ですが、感染症まで考慮した適切な処置を受けることが出来ます。
ここまで、主な良く出会う危険生物を紹介しました。
その他の出会った事のある生き物は・・・
ツキノワグマ。
山の藪の中で相手は山の上側。お互いに見えない状況で、異様な雄たけびの様な鳴き声の後、物凄い勢いで山の斜面を掛け降りて・・・人
間では掻き分けて進む
のに難儀する程の藪でしたが、ドドドド〜と地響きがするほどの勢いで、谷底まで掛け降りて行きました。藪の中で僅かに見えたのは、ひ
とかかえ程もある真っ
黒い塊り。こんな生き物はツキノワグマしか居ないでしょう・・・もし体当たりでもされていたら無事では済みませんでした。
イノシシ。
ウリボウを稀に見掛けたり、鳴き声は何処からともなく聞こえる事があるのですが、大人のイノシシには滅多に出会いません。
唯一出会ったのは、山の山道。その時は、急に雨が降りだしたと思ったら、目の前が真っ白になるほどの強雨に雷まで鳴り出した時。
私は急いで車まで戻ろうと山道を登ってました。そんな時、山道の脇からひとかかえは余裕であるデカイイノシシが急に脇の藪から山道に
顔を出したのです。臭
いも視界も遮られてイノシシも私の存在に気付かなかったのでしょう・・・急に山道に現れたイノシシ・・・山道を真っ直ぐ登っていた私
が先に気付き、あまり
にビックリしたので、ガッ!!って、肺の中の空気を一気に吐き出してしまいました。(こんなん初めて。)イノシシも直ぐに気付いて登
り坂の下にいる私を見
下ろして・・・点点点・・・文字でも声でも表現出来ないのですが、グワ〜と言う異様な鳴き声を発しながら、山道を横切って出て来た藪
とは反対の藪の中へ消 えて行ってくれました。
距離にして30m近くあったと思いますが、こっちに駆け下りて来られたら、大変な事になってたでしょう・・・。
シカ。
山の中へ車を走らせ、車の中でお昼休憩中・・・山道脇の崖の中から、立派な角のオスの鹿が顔を出したと思ったら・・・山道を横切っ
て、反対側の藪の中へ・・・しかも!! そのオスの後ろから何頭ものメスがゾロゾロと・・・
奈良公園などで普段から見慣れていると違うかも知れませんが、普段見掛けないので、立派な角の鹿って、結構デカイです。
サメ。
広い無料駐車場があり、急深の海。この浜はいつもサーファーがうようよ浮いていて、オットセイの群れでも居るかのよう・・・それはさ
ておき・・・
私はもちろん、ビーチコーミングで浜を歩いていたんです。そしてふと・・・何気に海を見たんです・・・そ・し・た・ら・・・
沖には大量のサーファーが居たのですが、その沖と私の居る波打ち際との丁度真ん中辺りに、もうほんと、絵に描いた様な三角形のヒレが
泳いでる!! こんな
ん初めて見るので、驚きと感動(テレビなどで見るまんまやん♪的な)と、めっちゃ釣りたい!!とか、こんな場所にもサメって居るんだ
とか・・・あれこれ同
時に思いながら、注意を呼び掛けた方が良いかとも思ったのですが、絶対に声は届かない・・・海中のサメは人を襲う種類のサメなの
か!?、ヒレのサイズから
考えると大きくても1.5m程では?などなど・・・あれこれ躊躇しているうちに、そのヒレは海中に消えて居なくなったのです・・・
後で考えたら、その時は陸に居たので絶対の安心があって余裕でしたが、もし海にいたら・・・私は泳ぎが苦手と言うのもありますが、も
う壮絶なパニックになって・・・溺れてたかも。
ここからは、さらに余談。
生まれてから今までに噛まれたり刺されたりした生き物。
噛まれたもの:
イヌ(手。数針縫いました。)、ウサギ(足の指)、コウモリ(手の指(血は出ず))、シマヘビ、アオダイショウ、ムカデ、マダニ(こ
れは毎年何度も)。
刺されたもの:
野良猫(鋭い爪で手を串刺しにされて、雑菌が入ってグローブ状に・・・)、アシナガバチ(数種類)、トックリバチ、不明の地バチ(数
種類)、アイゴ(何度も)、クラゲ(弱毒のもの数種類)、イラクサ、イラガの幼虫(デンキムシ)、蚊。
カニ・クワガタ・カマキリなどに挟まれたり、釣った魚のヒレが指に刺さったり、藪に入ってススキなどの葉で切ったり、ノイバラのトゲ
に刺されたりは、これからもずっと続くのでしょう・・・小さな流血は、ほぼ毎回の様にある・・・サバイバルに流血は付き物です・・・
