食用不可
目のようなものが右側にみえます。
左が良く見掛けるもの。右は細かなマダラ模様で目はわかりませんでした。
ウスヒラムシ。ながむし類。
体長2cm。薄っぺらいナメクジのようにヌメヌメクネクネと這い回ります・・・


水面下をとても良く泳ぎます。ヒラヒラ〜
捕獲して観察後、放したらまた、ヒラヒラ〜

ヒラムシ類。
ネットを検索しても情報が少ないです・・・不明。
エイのようにヒレをなびかせて泳いでました。
ウロコムシの仲間。ゴカイ類。
背側に鱗の様な板が連なっています。
ゴカイの仲間でもあるので、釣りエサに使えるかな?
ミズヒキゴカイ。ゴカイ類。
磯で砂の中からピンク色のヒモ状のものが出ていました。
イトミミズの様に1本1本が1匹の生き物ではなく、このヒモ状のものは鰓糸と呼ばれるもので、砂の中深くに本体が隠れてます。

ダイダイイソカイメン。
こんな外見で動物です。
上から。
裏側。
とても細かな毛のような小さなトゲが表も裏もビッシリ・・・ハリマンボンか・・・
生体反応無さ過ぎ・・・ですが、目を凝らしてよく見ると、このトゲがウネウネと動いてました。
裏側にひとつだけ穴が・・・肛門かな?
スカシカシパン。
直径11.5cmでした・・・直径14cm程にまで成長するとか・・・
黄色っぽい液体を出したのか・・・これが原因か分かりませんが、兎に角、臭い。
硬く薄っぺらで、とても細かな短いトゲ・・・一度裏返ってしまったら、自力では元に戻れないでしょう・・・また、とても平坦な砂浜しか歩けないのでは・・・体を貫通する大きな穴・・・生物としてあまりに不思議なので、次から次へと疑問が湧いてきます・・・
3月中旬。大潮で風無く波穏やかな日。辺り一面カシパンだらけ・・・これほどの状態は初めて見ました。
ハスノハカシパン。
裏側を見ると葉脈の様な筋があり、ハスの葉を連想させるのでこの名前になった様です。
8割がた砂の中に埋まっていたのですが、もしや!?と連想出来ました。
裏側を見るとフサフサな感じがありますが、一本一本の“足”は硬いです。
磯で良く見掛けます。これは石の裏側にビッシリと・・・
各自、思い思いの方向へ・・・
右側が鰓冠(さいかん)と呼ばれる、管から外に出てくる部分です。
カンザシゴカイ。
色々な種類がありますが、これは体長2cm程でした。巣の直径は1〜2mm程度。
ケヤリムシ。
この仲間のエラコは漁師が食用にもするようなので、もしかしたら・・・これも・・・とも思いましたが、ケヤリムシ自体の食用情報は見つかりませんでした。
個人で挑戦して食べた方の情報があったので、多少は食べても問題はないようです。
ほんの僅かな人影でも硬い管状の殻の中にサッと引っ込んでしまいます。
ベニクダウミヒドラ。
低水温で活動するとか・・・海水温が低く足が痛い!感覚が麻痺するほど冷たい海に足を浸けて数時間散策・・・
塹壕足症候群の記憶が頭をよぎりながら・・・海から出てもなかなか感覚は戻りませんでしたが、足は腐ることなく無事でした・・・そんな冷たい海で見つけた生き物です。
アマモの葉に着いてました。

ヒメホウキムシ。
4月上旬。岩に白い塊り・・・何かの卵かと思いました。良く見ると綺麗です。
オカメブンブク。
ピンポン玉程度の大きさで、手触り良く可愛いです。
砂の上に置いたら・・・ジワジワと潜って行きました♪
クロガヤ。
2月下旬。磯の岩場にて。
海藻の様ですが、クラゲやイソギンチャクに近い仲間です。
刺されると強い痛みがり、腫れ上がるので触らないように・・・

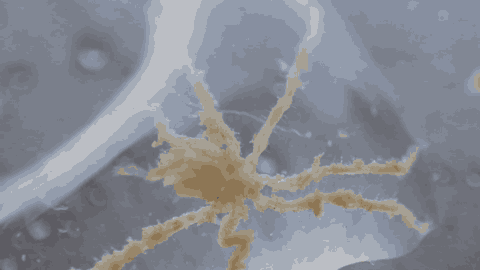
ウミグモの一種。
脚の関節は幾つあるのだろうか・・・これを器用に動かせる事が凄い♪
