甲虫類
ノコギリクワガタ。
メスが樹液を吸っている間、オスはメスが敵に襲われない様に守ってました。
2021年・・・サバイバルを始めて11年目・・・今まで一度も撮ってなかったなんてほんとビックリ♪

オスもメスもずっと下を向いていたのですが、スズメバチが近づいてきたら・・・オスはサッと向きを変えて威嚇!!
スズメバチは速攻で退散!!

小雨の中・・・レンズが曇ってイマイチですが・・・
最初は右の“クワ”が真っ直ぐな小型タイプのノコギリクワガタだけだったんです・・・
初めて撮影♪ なんて思っていたら・・・
のっし、のっし、のっしって、下から大きなノコギリクワガタ(写真左のもの)が登って来たと思ったら!! ガシガシって!! 小型の
ノコギリクワガタは、全く太刀打ちできず、あっと言う間に退散!!
小型のノコギリクワガタは蜜に集まっていたわけでもなく、ただ居ただけ・・・だったので、大型のノコギリクワガタは、あっと言う間に
追っ払ったら・・・何事も無かったかのように、さらに上に登って行ってしまいました・・・ただただ目障りだっただけか!!!

ふと・・・足元を見たら・・・ガサゴソと・・・ノコギリクワガタがウロウロ・・・

オスの小型個体。


ノコギリクワガタ <鋸鍬形>
シンプルでかっこ良いクワガタです。
2011年。山道を歩いていたら上から落ちて来たもの。

2019年。8年ぶり!! とても高い場所だったので、望遠で撮影・・・

2019年。2匹目! ただ、ちょっと雰囲気が違う・・・ミヤマクワガタとノコギリクワガタを足して割ったような・・・アゴの小さい
タイプ。

これも小型タイプ。

メス。デカかった・・・



オスに守られながら樹液を吸うメス。

オスの下にはメスが♪

ミヤマクワガタ <深山鍬形>。
子供の頃は、一番好きなクワガタでした。
変わった形の生き物が好きで、シュモクザメも好きでした・・・
今はもっとシンプルでオーソドックスなノコギリクワガタの方が好きかな・・・
小型のヒラタクワガタ。目測4cm未満程度。
目測で5cm以上〜6cm未満程度。
体長6cm。

この木のウロには毎年、大型のクワガタが住み着きます・・・
出て来たクワガタは・・・デカイ! 6cm以上はありそうです。 近くにメス2匹も!!

7月中旬。

8月上旬。体長5cm少々。

8月上旬。体長5.5cm。
クワの形が直線的なやや変わったタイプ。

ヒラタクワガタ <平鍬形>
アゴの力はハンパなく・・・虫かごを挟んだら一晩中そこにぶら下がってました・・・挟まれたら相当痛そうです。
上がオス(アゴを含めて2.5cm)、下はメス(アゴを含めて2cm)。
樹液に集まっている写真2枚は別の日・別の場所・・・どちらもメスが樹液を吸っていてオスは周囲を警戒していました。

オスの小型個体。

スジクワガタ <条鍬形>
オスでもクワが小さく、メスに良く似た固体もいます。
小さくて可愛いです。

7月中旬。オス。

7月下旬。オス。
これは大型個体でした。風格ある・・・

7月中旬。メス。
8月上旬。


コクワガタと言えど・・・やはりオスの大アゴは樹液を吸うには邪魔なようです・・・

コクワガタ <小鍬形>
一番見かける種です。あまりにも良く見かけているので、撮影していないなど思いもよらず・・・2016年まで撮ってませんでし
た・・・

ネブトクワガタ <根太鍬形>
10月下旬。木のすき間に“はさがって”いて・・・何とか取り出した瞬間!! 落ちた!!
その後、どんだけ地面を探しても見つからなかったのです・・・

6月中旬。あちこちで・・・


コガネムシ <黄金虫・金亀子>
これが正真正銘の正式名称コガネムシです。
写真はシャクチリソバの葉を食べています・・・若干、酸味のある美味しい葉です・・・私も食べます・・・
ミドリのメタリックがとても綺麗。
金属光沢が素敵・・・
緑色の個体がとても多いのですが、まれに青藍色の個体も存在します。
ヒメコガネ <姫黄金虫>
体色のバリエーションが多いです。




ヒメスジコガネ <姫筋黄金虫>
可愛いです・・・似た種が多いので同定に迷います・・・
頭部と胸部の縁は黄褐色。胸部に縦の凹み。翅のスジはオオスジコガネほどハッキリしない。










オオスジコガネ <大条黄金虫>
スジコガネとオオスジコガネはとても良く似ています。
スジコガネ:前翅の点刻がやや密で、前胸部のスジは弱い。
オオスジコガネ:前翅の点刻がまばら、前胸部のスジは深い。光沢が強い。
頭部と胸部は緑色、翅はブドウ色。全身赤銅色など変異もある。
※言葉で知っても・・・実際に2つを見比べないとわからん!!
2021年、2つの翅の写真を並べたものを見つけたのです!!
そして・・・過去に撮ったスジコガネの写真と比較したら・・・これはオオスジコガネだった!!
いつか・・・ただのスジコガネを見つける事ができたら、2つを載せたいです♪

似た種が多く、これは!?
今まで見た、良く似た種よりも一回り小さく、全体的にスリムで雰囲気が違ったので撮影しました。
(お尻の先に向かって、やや幅広となり、ずんぐりした印象のコガネムシ類と違い、お尻の先の方までほぼ真っ直ぐでスリムでした。)
いつか分かるかな!?

ひとつ上と同じ種!? そして恐らく・・・だいぶ雰囲気が違う(テカリ具合など)様に見えますが、光の加減の様です。
恐らくヒメスジコガネだと思われます。
※サクラコガネ、ヒメサクラコガネ、チビサクラコガネ、ヒメコガネ、ヒメスジコガネ、ツヤコガネ、スジコガネ、オオスジコガネな
ど・・・似た種が多いです。
これらを完全に見分ける方法をだれか公開して♪

この緑の光沢を表現したかったのです・・・


全体的に赤味のある個体。

マメコガネ <豆黄金>
草むらでよく見かけます。頭と胸が緑、羽が茶色の小さなコガネムシです。
後ろの足2本をアンテナの様に上げている姿も良く見ます。
子供の頃は、あちこちで沢山見た記憶があるのですが、最近はほんと僅かに見掛けるだけ・・・そんなマメコガネですが、海外では“ジャ
パニーズ・ビートル”と呼ばれ、農業被害が拡大しているようです・・・

カタモンコガネ
色の無いマメコガネかと思ってました・・・


別種かと思いましたが、こんな色の個体も居ます。


こちらは、じっくり見ないと模様がわからない。

薄暗く写りが少し悪いですが、デカかった。
体長は図鑑をみると、8mm〜13.5mmとか・・・これはほぼMAXサイズでした。


セマダラコガネ <背斑黄金>。
子供の頃から時々見かけてましたが、図鑑に載っていなかったので名前が分らず・・・初めて知りました・・・



ドウガネブイブイ <銅鉦蚉蚉>
捕まえるとフン(軟便)を沢山出すので、虫かごが直ぐにフンでベトベトになります。
子供の頃から捕まえてもあまり嬉しくない虫でした・・・

上がドウガネブイブイ。 下はアオドウガネ。
同じ向きでヤブガラシの密を吸ってました。


アオドウガネ <青銅鉦・青胴金>
ドウガネブイブイ同様にギラギラの光沢ではありません。
樹液に集まる虫達。
アオカナブン <青金蚊>
クロカナブン <黒金蚊>
オオゾウムシ <大象虫>
マダラアシゾウムシ <斑脚象虫>



クロカナブン。
フラッシュを焚きましたが、黒光りが良い感じに写りました。
クロカナブンは数が少ないようです。


やや緑色ですがノーマルのカナブンでしょう・・・

こちらもカナブン(緑色タイプ)。この濃い緑色も綺麗。
カナブン。茶色や緑色などバリエーションがあります。


赤味を帯びた茶色バージョンですが、緑色も混ざるタイプ。

ブクブクと樹液が出て来る場所にて・・・カプチーノ状態。


樹液の奪い合
い:(YouTube動画)
近づくとぶつかり合う音がガチガチ・・・と聞こえました。小さいけど迫力ある♪



アオカナブン。
この世のものか・・・とても美しい緑色・・・写真ではなかなか表現しきれないので、捕まえてみました・・・腹側も・・・全身全て光沢
のある緑色でとても綺 麗です。


カナブン <金蚊>
樹液に集まっていると、まるで宝石を散りばめたようです。
人の気配に気付くと飛んで逃げる事も多いです。
単純に黒、茶、緑だけでなく、青緑や赤、紫まで・・・超レアですがいつか撮りたい・・・
右:カナブン、中央上下:シロテンハナムグリ、左:アオカナブン。
左右上がシロテンハナムグリでそれぞれ茶色・緑色バージョン。中央の上中下はカナブン。



体の掃除をしながら、ちょいと休憩・・・

シロテンハナムグリ <白点花潜>
他のコガネムシは硬い前羽を広げて飛ぶのでプロペラ機の様にゆっくりぶ〜んと飛びますが、カナブン、ハナムグリの仲間は、固い羽を閉
じたまま、中の羽だけ 出して飛ぶのでジェット機の様に高速飛行できます。
良く似ているものにシラホシハナムグリがいます。
シラホシハナムグリ。
今まで何年も!! ハナムグリを見つける度に探してました・・・やっと見つけた!!
写真左がシラホシハナムグリ♪ 他のハナムグリと模様が違うのが分るでしょうか♪
ヌルデの花粉を食べるコアオハナムグリ。塩っぱくないのかな?

ふたりで♪

コアオハナムグリ <小青花潜>
小型のハナムグリで毛に覆われています。白い斑紋が大きいのも特徴。
アブラナの花で。


お花畑で恋をして〜♪





ナミハナムグリ <並花潜>
コアオハナムグリよりも大きいです。コアオハナムグリ同様に毛深いのですが、前胸部の縁が紫色で白い斑紋は小さく、お尻に近い部分に
は波“〜”状の模様。
アオハナムグリ <青花潜>
コアオハナムグリよりも大きく、ナミハナムグリとほぼ同じ大きさです。
ナミハナムグリと異なり、こちらは毛が無いか少なく、脚や腹部は鮮やかな銅色です。
良く似た3種の特徴まとめ:
・コアオハナムグリ
他の2種に比べて小型。毛深くて白い斑紋が大きい。肩部に白斑がある。(無いものもいる)
・ナミハナムグリ
コアオハナムグリよりも大きくて、同じように毛深い。
前胸の縁に紫色の金属光沢がある。斑紋は細め。
・アオハナムグリ
コアオハナムグリよりも大きくて、アオハナムグリと同じ程度の大きさ。
毛は無いかやや毛が生える程度で3種中最も毛が薄い。
前胸の縁に紫色の金属光沢がある。
3種中地色の緑が最も濃く、背面の金属光沢は最も強い。
肢や体下面は鮮やかな銅色である。

キョウトアオハナムグリ。
山の中で撮影。木のだいぶ上の方に居たので、これで精一杯でした・・・
遠くから数枚撮影しただけですが、緑色は濃い・全体的にマット状・前胸部にも白班が多く、縁のラインが特徴的・見た感じではナミハナ
ムグリと同じ程度の大きさでした。

上はナミハナムグリ。下がクロハナムグリ。

クロハナムグリ <黒花潜>
まれに見掛けますが、コアオハナムグリに比べたら・・・何十分の一!



ヒラタハナムグリ。
背中が平らで後ろ足が長いです。とても小さいハナムグリ。

アシナガコガネ。

ヒメアシナガコガネ <姫足長黄金虫>

7月上旬。

オス。7月中旬。


6月上旬。メスかオスの黒化型か・・・雄の通常型はもっと綺麗なのです・・・

メス。
オオトラフコガネ <大虎班黄金虫>

コイチャコガネ <濃茶黄金虫>
体長1cm前後の小さなコガネムシです。可愛い・・・

だいぶ、粉が落ちてますがコフキコガネでしょう・・・


クルミの葉を食べている所。

コフキコガネ
きな粉に似た色の細かな毛が生えているのです。
ヒゲコガネ。
子供の頃から、1度か2度か・・・滅多に目撃することはありませんでした。
サバイバル生活を初めて6年目にしてやっと・・・見事なヒゲ(触角です・・・)。 存在感あります。



ビロウドコガネ。
子供の頃は良く見掛けました。懐かしい・・・久しぶり♪

クロコガネ。
似た種にコクロコガネやオオクロコガネがいます。

キスジコガネ。山の中・・・落ち葉の上を歩いてました。
コガネ類。
東南アジアでは、成虫丸ごとを揚げたり、炒めたりして食べられています。

柔らかい葉の付け根部分をカジッてました。


何故か手前の個体の首に手をまわしてました・・・
センノカミキリ <栓の髪切>
別名:センノキカミキリ <栓の木髪切>
写真の様にタラノキで見掛けます。毎年、この場所に来ると良く見つかる事がわかりました。
アトジロサビカミキリ <後白錆髪切>
サバイバルを始めて間もない頃に撮影したもの・・・カミキリムシとカメラの間に草があったようです・・・
写真の葉・・・クワの木を食害するようです。

クワの木にて。


キボシカミキリ <黄星髪切>

緑色っぽいもの、水色っぽいもの・・・色や大きさなど、違う個体も見掛けます。

やはり、メスの方がひとまわりデカイです。
交尾は10数秒程度で、あっという間に終わってしまいました。
とても好奇心旺盛なのか・・・撮影していたら彼方此方でこちらを凝視・・・
何故、ラミーに居ても目立つこんな派手な模様なのかといつも疑問でした。
偶然かも知れませんが、ラミーの枯れ葉に留まっていると目立ちません・・・
ラミーカミキリ <ラミー髪切>
こちらは、写真の葉・・・カラムシの葉を食べます。

6月中旬。
7月上旬。

7月下旬。キノコの撮影をしていたら、ガサゴソガサゴソと・・・何かが近づいて来る!!
見たらノコギリカミキリ♪ ただ、延々とせわしなく歩き続けて止まらん!!

あちこちウロウロ・・・歩き続けて止まらない・・・大量に撮影してやっと綺麗に撮れた1枚。

8月中旬。
触角が太く、第3節よりも第4・5節を合わせた長さの方が長いので、オスのノコギリカミキリと同定しました。
ノコギリカミキリ <鋸髪切>
体長2.5cm。これは小さな固体でした。
やたらと動き回り、触角が長く・・・掴むとキーキー鳴き・・・とてもせわしない生き物です・・・ゴキブリっぽい感じもあるので苦手な
人もいるのでは?
触角の太さによりオスとメスを、オスは第3・4・5節の長さ、メスは先端の節でノコギリカミキリかニセノコギリカミキリかを見分ける
事が出来ます。
触角が細く、先端は第11節で凹みがあるので、メスのニセノコギリカミキリと同定しました。
ニセノコギリカミキリ
ノコギリカミキリととても良く似ているので、ニセノコギリカミキリと言う種を知らないと、全く気付きません。
私も新しい多くの種が載っている図鑑を買って初めてその存在を知りました。


クワカミキリ <桑髪切>
桑やケヤキの木を食べるようです。
外灯近くにて・・・だいぶ弱ってました。
ミヤマカミキリ <深山髪切>
胸のシワが特徴です。
複眼が触角の後ろをグルッと周り込んで・・・どうやって見えているのか・・・
見つけたのは橋の下・・・河原に生えているクヌギにて。
橋には外灯があり・・・触角が片方切れているので夜間に外灯と戦っていたのでしょう・・・

木のウロで休んでました。

ウスバカミキリ <薄翅髪切>


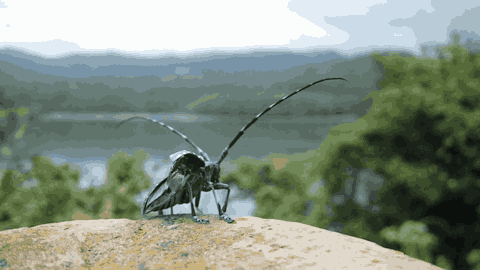
ゴマダラカミキリ <胡麻斑髪切>
カミキリムシの中で一番身近な存在ではないでしょうか。
みかん農家にはもっとも嫌われる存在・・・子供の頃、親戚のおじさん(みかん農家)が、見つけたら首を捻って殺していたのにショック
でした・・・時は流 れ・・・私は普通に食べてたり・・・




シロスジカミキリ。
図鑑では体長4〜5.5cmとなっていますが、6cmは十分にあったと思います。
子供の頃からの憧れでした。デカイ!! 迫力があります。 咬まれない様に注意!!
不明。
手持ちの本やネット上の図鑑には似ているものも見つかりませんでした・・・
ゴマダラカミキリのようなガッシリした体でした。

ヒメヒゲナガカミキリ。
セイタカアワダチソウの葉の上で、体の手入れをしてました。

セダカコブヤハズカミキリ。
翅が退化して飛ぶことが出来ないため、地域により少しずつ特徴が異なるとか。

チャボヒゲナガカミキリ。
9月下旬・・・ずっと降り続く小雨の中・・・木のうろで雨宿りしてました。


ヤツメカミキリ。
サクラの木にて。一説によると、上の写真にも写っているウメノキゴケ(写真左上の緑色の地衣類)に擬態しているとも言わます。

キマダラミヤマカミキリ。

クロカミキリ。
2018年、生きているものはサバイバルを始めてから初。

ナガゴマフカミキリ。


ルリボシカミキリ。
2025年! 生まれて初めて見ました♪
ブナの育つ1,000m級の山にて。

シラホシカミキリ <白星髪切>

クビアカトラカミキリ。
伐採されて積み上げられた樹木に居ました。

ヨツキボシカミキリ <四黄星髪切>
カミキリムシは、派手な模様の種類が多いと、今更ながら思った2020年・・・





フタオビミドリトラカミキリ。
その名の通り・・・翅に黒い帯が2つある、緑色のトラカミキリです。
残念ながら?写真の様に黒い帯は個体により無いものもあります・・・


エグリトラカミキリ <抉虎髪切>


キスジトラカミキリ <黄条虎髪切>

トラカミキリの仲間。
山の中、道路沿いにある看板の支柱にて。
ネット上の写真を探し回りましたが、この模様と同じものは見つからず・・・ほんと・・・種類が多い・・・
2025年・・・↓ひとつ下と同じかも!?



ニイジマトラカミキリ。
薄暗い山の中で、歩き続けて止まらん!! ふと、別の個体が木の又に・・・そっと撮影した直後・・・歩き出した!!
人の気配を良く察知する上に、一度歩き出したら永遠に止まらない・・・
またいつか、綺麗に撮れたら差し替えます♪


ウスイロトラカミキリ。



トゲヒゲトラカミキリ。ヤブデマリの花に集まってました。

トラフホソバネカミキリ。
意外とかわいい顔です。
キクスイカミキリ <菊吸髪切>
菊に付く害虫・・・写真はヨモギですが、ヨモギもキク科なのでした。


シラハタリンゴカミキリ
リンゴカミキリの仲間・・・調べたら色々な種類が・・・
良く似たニセリンゴカミキリは、愛知県以西、このシラハタリンゴカミキリは静岡県以東です。
※温暖化などの影響で変わって来ているかも!?


ヘリグロリンゴカミキリ。
良く似ているニセリンゴカミキリは触角が黒色です。
翅の黒い部分は、全体ではなく、“ヘリ(端)”だけなのが特徴です。


ホソキリンゴカミキリ。
腹部の第1〜3腹節が黒いのです。


ホソツツリンゴカミキリ。

クロハナカミキリ <黒花髪切>

交尾中・・・つい・・・そこへ・・・目が行ってしまいます。 なんと・・・半透明の・・・ちん・・・もとい、生殖器。
アカハナカミキリ <赤花髪切>
やはり、赤い色はすぐに目につきます。

モモブトカミキリモドキ。
3月下旬。クサイチゴの花にて。

ヨツスジハナカミキリ。
7月上旬、リョウブの花にて。


オオヨツスジハナカミキリ。
ひとつ上と同じく、7月上旬、リョウブの花にて。
“オオ”と名前にあり、実際、大きいようですが、今回見たものはどれも小さい・・・花の大きさから分かるでしょうか・・・ヨツスジハ
ナカミキリと同じ大き さでした。
ほんと、あっちでも♪ こっちでも♪

上と同じくオオヨツスジハナカミキリ。朽ち木で産卵中。
このオオヨツスジハナカミキリは、地域により色合いが様々で、だいぶ黒くなる個体もいるとか・・・
この個体は、かなり黒く、翅の黄色も僅かなだけでなく、全ての脚も黒!!

ニンフホソハナカミキリ。
カミキリムシ類。
カミキリムシの薬効:頻尿、尿失禁、夜尿症など
東南アジアでは、揚げる、炒る、焼くなどで食べられています。

鳥のフンになりきっている!?
何となく・・・私が子供の頃に流行った記憶が僅かにある・・・“ダッコちゃん人形”を思い出しました。
※“ダッコちゃん人形”の始めのブームは私の生まれる前だったようです・・・私の記憶はリニューアルした時のものかな?



オジロアシナガゾウムシ <尾白脚長象虫>
クズの葉の上で良く見かけます。
良く見たら背中にアリ? そんなものは気にしない・・・「自分、不器用ですから」・・・

イタドリの茎の上にて。
マダラアシゾウムシ <斑脚象虫>
樹液に集まります。ゴツゴツと武骨な感じが良い雰囲気を出してます。
クリアナアキゾウムシ。
これは恐らくの同定・・・とても良く似たゾウムシにマツアナアキゾウムシなどが存在します。
ヤブマメの葉を食べてます。
シロコブゾウムシ。
何となく・・・馬のような・・・象ではなく馬?
意外と可愛い顔です。




不思議な色だと思ったら・・・イタドリの茎の色に似て・・・見事に溶け込んでます・・・


カツオゾウムシ <鰹象虫>
あちこちのイタドリの葉の上で見掛けました。
橙色の粉は次第に落ちて地味になっていきます。
ホオジロアシナガゾウムシ。
顔の横が白っぽく、他の足に比べて前足が長いです。

雨にも負けず・・・まさに濡れ場・・・
ハスジカツオゾウムシ。
ヨモギの上で良く見掛けます。
キスジアシナガゾウムシ <黄条足長象虫>
山中、イタドリの葉の上にて。





コフキゾウムシ。
クズの葉の上で良く見掛けます。かわいい・・・


ヒレルホソクチゾウムシ
体長1.8mm程度の超小さいゾウムシです。
ちなみに、左の実はウツギです。



ウスイロヒゲボソゾウムシ

不明。
ネット上の図鑑をあれこれ検索しましたが、同じ外見・模様の個体は見つかりませんでした・・・
体長1cm弱のゾウムシでした。

不明。


イネミズゾウムシ
田んぼの土を少しばかり頂いて水を入れ・・・何か微生物でも出て来ないか・・・
で、翌日。!?
微生物どころか、体長4mm程のゾウムシが!! しかも水中を泳いでる!!!
なんて不思議な生き物・・・しかも調べたら、雌だけで増えるとか・・・


スナムグリヒョウタンゾウムシ。
ハマヒルガオの花の中に居ました。

アカコブコブゾウムシ。10月下旬。雨上がり。
横から陽が差してゾウムシのゴツさが良かったので思わず♪


ヤマブドウの葉の上に何匹も・・・みんな体を持ち上げて硬直姿勢・・・
ブドウハマキチョッキリ。
ハイイロチョッキリ。
何となく・・・鳥のキーウィを連想させます。
このなが〜い部分は鼻では無く、口です。

クチナガチョッキリ。アオツヅラフジの実に穴を開けてました。

グミチョッキリ。アキグミの花が咲く4月上旬。

イタヤハマキチョッキリ。


ドロハマキチョッキリ。
ゾウムシ類。
東南アジアでは揚げて食べられています。

ヒゲナガオトシブミ。
首がなが〜いです。

ヒメクロオトシブミ。
私宛てにひとつ・・・お願い! ・・・なんて♪
メス。
シモフリコメツキに似ていますが、触角の節の長さなどで判断します。

薄暗い林下で動き回り・・・ブレてます・・・

オス。
ヒゲコメツキ。
オスだけ、このような触角になります。



クシコメツキの仲間。



ニホンベニコメツキ
毒のあるベニボタルにそっくりです。
オオクシヒゲコメツキ。
体長3.5cmほどになります。大きい・・・
捕まえるとパッチンパッチンと連続技を披露してくれます。
不明。
良く見かけるものよりも太くてズングリしている感じだったので撮影してみました。
フタモンウバタマコメツキ。
でかい・・・体長36mm。(私の図鑑では最大32mmとなってます。)
これはタマムシサイズ・・・個体数が少なく、目撃するのは稀だそうです・・・

ウバタマコメツキ。

子供の頃の記憶が間違いでは無かった・・・サビキコリはこうやって臭い攻撃もします・・・
臭い攻撃はやる個体とやらない個体がいるのだろうか・・・
サビキコリ <錆木樵>
変わった名前です。

コメツキムシと言えば・・・
ひっくり返すとパチッっと首を折って飛んでいくのが面白い・・・子供の頃は遊びました。
上はカメラに激突した後、スタコラ逃げていく姿が面白かったのでつい・・・


ウバタマムシ <姥玉虫>


6月上旬。今まで何度もここに来ていました・・・今回も・・・僅かに体が見えて偶然気付いただけ・・・




アオマダラタマムシ <青班玉虫>
想像以上に良く歩き、飛びます。
しかも・・・人の気配を感じて木の裏側に身を隠します・・・
玉虫はノソノソと動くイメージがありますが、これは違ってまるで忍者か?
ヤマトタマムシに比べて小さいので気付き難いです。

シロオビナガボソタマムシ <白帯中細吉丁虫>
漢字名を調べたら吉丁虫? “吉丁虫”で調べたらこれでタマムシと読むこともあるようです。漢字名では、“白帯長細玉虫”も見つかり
ました・・・“中細” と“長細”も違う・・・
名前は“白帯”ですが、写真のように青味がかった“白帯”の個体も居るようです。
体長1cm弱の小さなタマムシでした。

クロナガタマムシ <黒長吉丁虫>
地域により色彩変異があるようですが、黒に、このブルー・・・綺麗♪

ムネアカチビナカボソタマムシ。アカメガシワの葉にて。

コウゾチビタマムシ。
チビタマムシの仲間は、小さい上に情報も少なく・・・同定に迷うと思われます・・・
今回は、コウゾの葉の上で見つけた事、ネットで調べたコウゾチビタマムシの模様とほぼ同じだったので間違いないでしょう。



クズノチビタマムシ。
クズの葉の上にて。

タマムシの群れ。
この1本の木に何匹いるのだろうか・・・常に5〜6匹が飛び続け・・・枝や葉に何匹いた!?
それはさておき・・・飛行している時の形!! ぶ〜んって飛んでいる姿が目に入った時、この形だったらタマムシです。
ちなみに、コガネムシ系は翅が短いので、大袈裟に表現するとミッキーマウス的な感じに。
カナブン系は、外側の翅を閉じているので、ジェット機の様に高速飛行。
大きさや翅の長さが似ているカミキリムシは、触角が長いのと、全ての脚を広げている&超低速飛行なので分かり易い♪

綺麗な色をそのままにカメラに写すのが難しい・・・
高速に脚をバタバタ動かしていたので写ってませんが、脚はちゃんとありました。



産卵中のタマムシ。



ヤマトタマムシ <大和玉虫>
実物はとても綺麗なのですが、写真に撮ると綺麗さが伝わり難いです・・・
目と足の裏以外はキンピカ・・・なぜこの様に進化する必要があったのか・・・
タマムシ類。
タイなどでこのタマムシも食用にされるのですが、羽は装飾用に取り除いてから調理されるようです。
揚げる、炒る、焼くなどで食べられています。
ウリハムシ。

キイロナガツツハムシ。

ギシギシとイチゴハムシ。
クロウリハムシ。
写真の植物はアレチウリ。
ヨモギハムシ。

バラルリツツハムシ。
イタドリの葉に居ました。


コガタルリハムシ。
ギシギシの葉にて。
キボシルリハムシ。

クロボシツツハムシ。

ヤツボシハムシは色彩変異が激しいので写真のような模様のハッキリしないものも居るのでした。
ヤツボシハムシ。
その名の通り翅には4つずつの班があるハムシです。

クロボシツツハムシ。

ドウガネツヤハムシ <銅鉄艶葉虫>
タラノキに良く着いてます。
青黒い感じのものはアオグロツヤハムシです・・・そのまんま。

ムナグロツヤハムシ。超可愛い♪♪♪

キアシヒゲナガアオハムシ。

アカガネサルハムシ。

イタドリハムシ。

フジハムシ。
3月下旬、フジの葉を食べるハムシですが、ヒイラギの葉の上で。

テントウノミハムシ。
ヒイラギを食べるハムシ。ヒイラギの木に居ました。
黒地に赤紋・・・テントウムシに似ていますが、触角が長い!! 他の生き物は騙せても私は騙されん!!
早速、ハムシの仲間で調べたらやっぱり♪ 触角が短くなるように進化したら間違うかも!?
ムナキルリハムシ。
ヒゲナガハムシの仲間。
フタホシオオノミハムシ

ルリマルノミハムシ。
光沢があり、後ろ脚が太いのが特徴です。
10月上旬、薄紫色のヨメナの花にて。

イチモンジカメノコハムシ。
撮影していたら顔を僅かに見せてくれました。ちらっ♪



セモンジンガサハムシ。
背中に金色の紋と、グルッと一周する金色の帯・・・美しい♪ 金箔細工のよう・・・

ヨツモンカメノコハムシ。
ヒメジンガサハムシ。
渋い・・・地味・・・です。

ホソクビナガハムシ。
良く似た種が幾つかあります。ちなみに、写っている植物はサルトリイバラです。


キイロクビナガハムシ。
幼虫は糞を背中に乗せるとか・・・

アカクビナガハムシ。
キイロクビナガハムシに似ていますが、こちらはツヤがあります。
写真の植物・・・サルトリイバラを食べるハムシです。

アカガネハムシダマ
シ。

セラネクイハムシ。
コウホネにいたハムシなので、コウホネネクイハムシかと思いきや! 生息域が限られている珍しいセラネクイハムシのようです。
ネットで調べたら、この池でも生息が確認されていました♪
ハギツツハムシ。
色が個体により変異が大きく、写真の様な個体から、黒い個体まで様々なようです・・・今回は、このイタドリに何匹か居たのですが、全
てこの様な色合いでした。
ハギやヤナギを食べるそうですが、何故かイタドリに・・・ネットを調べたら、やはり何故かイタドリにいる写真も見つかりました・・・
その関係性は!?

ヒメマルカツオブシムシ。
子供の頃は良く見掛けていました・・・白いキク系の花に付いてる小さな虫・・・今回、名前を調べて初めて知りました・・・花に集まる
人畜無害な虫・・・と思ったら!!
この虫の幼虫は・・・家の中に入ってしまうと、植物性だけでなく動物性も含め、衣類に穴を開けられてしまったり・・・カツオ節など乾
燥食品も食べられてしまうとか!! これはほんとに幼虫意!!

1月中旬。


2月上旬。

4月中旬。

4月下旬。


5月上旬。

5月中旬。

6月上旬。
この子だけか!? 結構・・・もじゃもじゃ・・・
11月上旬。
ナナホシテントウ。
説明不要ですね・・・可愛い・・・

大きな赤い2つの紋。


変形した2つの紋。

オレンジ色の紋の中に黒点があるもの。
赤地に黒点が沢山あるもの。

これもナミテントウ・・・

海岸で汚れたテントウムシ・・・見た事が無い種類だと・・・調べたらこれもナミテントウ。

これもナミテントウ・・・

ほぼ紋がないもの・・・


四紋型のナミテントウ。

恐らくこれもナミテントウ。

お食事風景・・・音も聞けたら「バキバキ」と聞こえてきそうです。

ナミテントウ。
模様が全然違いますがこれらはナミテントウです。

ダンダラテントウ。
ナナホシテントウやナミテントウよりもひと回り小さいです。
普段見ているテントウムシよりも明らかに小さかったので、ダンダラテントウかと思ったのですが、これもナミテントウのようです。
ちなみにダンダラテントウの特徴は、肩の辺りに必ず赤い斑が残る、触角の先は尖り気味、眼の間と触角の長さが同じ、翅のへりの反りが
大きい。


八重桜とナミテントウ。

とても歩くのが早く・・・やっと撮れたのがこの写真・・・
こんな模様ですが、これもヒメカメノコテントウです。

こんな模様も♪

模様の違うもの同士の交尾。

草陰での秘め事・・・ヒメだけに♪

よく見たら3匹で♪ 3P!?

こちらは、模様違いのペア♪ しかも食事中・・・って! デカ! 全部食べれる!?

ヒメカメノコテントウ。
小さなテントウムシで動きが早いのでボケぎみです。
ベニヘリテントウ。
ヤブマオの葉に居ました。
赤い縁取りが翅の外側だけのアカヘリテントウもいます。
良く見たら、前胸部の眼に近い部分は透明になってます・・・視界良好。
ムーアシロホシテントウ。
白色紋は、4−4−4−2です。




数が少ない黒色タイプ。
シロジュウシホシテントウ。
ムーアシロホシテントウかと思ったら・・・良く似てます! 翅の白点の数も同じ14!!
ですが、白点の配置が違うのです・・・
翅の上の白色紋は、2−6−4−2で、14です。
ナス科を好む事を知っているのですが、これはアカメガシワの葉・・・
良く見たら舐めている? 葉のこの丸い部分は何!?


ニジュウヤホシテントウ。
ナス科の植物を好んで食べるのは知っていましたが、最後の写真はヤブガラシの花をナメているのかカジッているのか・・・
改めて図鑑を見たら・・・ニジュウヤホシテントウ類!? 類!?
同定困難なとても似た種類が多いようで図鑑でも“類”で一括りにしていたのです。
この歳になって初めて気づいた事実!!


ハラグロオオテントウ。
体長1cm超。クワの実を採取していたら見つけました。
大きくて丸くてカワイイ・・・と思ったら“腹黒”だったとは・・・なんて・・・性格が悪いわけではありません・・・
黒色紋は、2−6−6。



カメノコテントウ。
体長1cm前後。
普通のテントウムシよりもだいぶ大きいです。
冬は集団で越冬します・・・子供の頃、川原で大量に見つけた記憶があります。

ジュウサンホシテントウ。
大量に居たのですが、動き回って上手く撮影できず・・・
黒色紋は、3−4−4−2。

マクガタテントウ。
河原のカワラヨモギに居ました。体長3〜4mm程の小さなテントウムシです。


アイヌテントウ (ジュウイチホシテントウ)。
河原のホオズキの葉の上に居ました。 葉っぱを食べてる!?
ぱっと見、ナナホシテントウに似てますが、星の数が違うのです・・・
黒色紋の数は、3−4−4。

クモガタテントウ。


ヒメアカホシテントウ。
3〜5mm程のテントウムシです。


一眼のマクロ撮影ではF8でもピントが合うのは顔だけ!


モンクチビルテントウ。
大きさ3mm程度の小さなテントウムシです。
ヨツボシテントウかと思ったら、紋が横長なんです。

コクロヒメテントウ。
こんな小さな虫・・・撮るつもりも無くなんとなく・・・とても小さな虫は数も多いし、図鑑で調べても分からないものばかり・・・なの
です・・・
今回はほんの気まぐれ・・・さてさて・・・ハムシの仲間!? どうも違う! もしかしてテントウムシ!?
・・・居た! 調べたら、このヒメテントウの仲間は種類も多い! 深入りしたら頭バクハツするでしょう・・・
体長は2〜3mm程・・・黒くて小さくて・・・地味〜



ベダリアテントウ。
イセリアカガラムシを駆除する目的で、この静岡県で100年前に導入されたテントウムシです。

アミダテントウ。河原にて。
超かわいい♪

フタモンクロテントウ。こちらも体長2〜3mm程!

キマワリ <木廻>
想像以上にあちこちに居ます。山へ行くと数匹はすぐに見つかります。
セスジキマワリの仲間。
詳細な図鑑など情報が手に入らないので、正確な同定は出来ませんでした。
(私の眼には、上の2種は別物に思うのですが、ネットを検索すると、どちらもセスジナガキマワリと紹介されてます・・・)


ヨツボシオオキスイ。
樹液に集まってました。


上の虫は!?


ヨツボシケシキスイ。
オオモンキゴミムシダマシ。
コロンと丸く、可愛い模様・・・手で思わず触ったら臭くなってしまいました・・・
ツガサルノコシカケを食べてました。


ニジゴミムシダマシ。
ゴミムシダマシの仲間。
こちらもツガサルノコシカケを食べてました。


ベニヒラタムシ。
横から見ると超薄っぺら!! それもそのはず・・・枯れ木の樹皮の隙間で生活してます。


獲物を狙ってます・・・獲物って・・・私!?

交尾♪

ニワハンミョウ <庭斑猫>
白い斑紋には変異が多いです。
通りがかる他の虫を食べるので強力なアゴを持ちます。
「道教え」の名の通り、私の前を飛びながら、一緒に山歩きしました・・・


コハンミョウ <小斑猫>
河原で見掛けました。


カワラハンミョウ <河原斑猫>
海岸で撮影しました・・・“カワラ”と付いてますが、海でも見掛ける種類です。


エリザハンミョウ。
海岸沿いの砂地で、山から染み出る水のある場所・・・歩いていたら、一斉にぶ〜ん♪って逃げる・・・
最初はコバエかと・・・何気によく見てみたら、ちっさいハンミョウ♪
今までニワハンミョウは彼方此方の山で見たのですが、正真正銘、正式名称“ハンミョウ”は始めて見ました。







ハンミョウ <斑猫>
小さい昆虫ですが、とても綺麗。

オバボタル。
とても良く動き回るのでカメラで捉えにくいです。

ムネクリイロボタル。
クシ状の触角が特徴です。

ベニボタル。
5月末、クリの花で交尾してました。

カクムネベニボタル。
一つ上のベニボタルを初めて見た日と同じ日・・・こちらも初めて。


ベニボタルの仲間。
ネアカヒシベニボタル、マエアカクロベニボタル、スジアカベニボタル、カタアカベニボタル、
ネアカクロベニボタル・・・など・・・どれも良く似ていて情報が少ないので同定せず・・・

ホタルの飛翔。
明るすぎない、ほのかな明かり・・・それが、ゆらゆら〜と、点滅しながら・・・風流♪

アオカミキリモドキ。
ニンフジョウカイの仲間。
セボシジョウカイ。
クビボソジョウカイの仲間か。
ニセヒメジョウカイでしょうか・・・
細かく分類しようとするほど情報が少なく・・・

カラシナの花とジョウカイボン。
これはセスジジョウカイかヒメジョウカイ。

アオジョウカイ
大きなホオの葉の上にて。

ムネアカクロジョウカイ <胸赤黒浄海坊>

ジョウカイボン
とても変わった名前です・・・
甲虫(カブトムシ、クワガタムシ、カミキリムシ、コガネムシ等)・・・どれも、外殻が硬いです。
大型のカブトムシ等は、手で割って中の肉のみを食べますが、その他は丸ごと頂きます。
硬い殻ごと食べれるような料理法が良いです。
唐揚げ、素揚げの時は2度揚げします。
写真は、マメコガネ多数に、ゾウムシ、コメツキムシ、ナナホシテントウ等。
ドウガネブイブイとウバタマムシ。
ミヤマクワガタ5匹、クワカミキリ、ウバタマムシ、キマワリ数匹、スジコガネ2匹等。
ミヤマクワガタのうち、右側3匹は小さい・・・これでもミヤマクワガタか・・・このサイズがバリバリ食べれる限界かな・・・大き目の
ミヤマクワガタは完全 に噛み砕く事ができませんでした・・・噛んで殻だけ出しました・・・
ちなみに、ミヤマクワガタは1箇所に群がっていて、一緒に居たメス3匹は逃がしてあげました。
虫は死ぬと足を丸めるので、盛り付けるといつも腹が上になってしまいます・・・綺麗なコガネムシなので、盛り付けを工夫して・・・フ
ワッと丸めたティッ シュに乗せる感じで綺麗な背が見えるようにしてみました。
上:カナブン4匹と左下:キマワリ、残りはスジクワガタのオスとメス。

ヒメスジコガネ。
とても綺麗なヤマトタマムシ・・・頂くにはライトアップして頂きましょう・・・
タマムシの実験でも行ないましたが、揚げると青い色に・・・その後、だんだん元の色に戻りました・・・
いろいろごちゃまぜ・・・ゴマダラカミキリ、ラミーカミキリ、マメコガネ、セマダラコガネ、キマワリ、ヒメスジコガネ、シロコブゾウ
ムシ、カツオゾウムシ など・・・見て楽しみながらサクサクとスナック感覚で頂きました。

コフキコガネ。 ちょいと少なかったのでミックスナッツと一緒にしてみました♪ 違和感ない♪

カナブン。
下にあるのは、アキノゲシの天ぷら。奥はニンニクの素揚げ。
蛍光灯の色で分かり難いですが、手前中央はクロカナブン。その右上の右隣あたりのものは、ノーマルタイプなのですが、僅かに緑色にも
輝く紫色の個体でした。
食べた感想は・・・コガネムシは柔らかいものが多いのですが、カナブンは・・・殻が結構硬くて口に残るので、良く噛んで頂きましょう
♪
素揚げ。
そのままの状態で油で揚げるだけ・・・とてもシンプルですが、硬い甲虫もサクサク頂けるのでお勧めです。
若干虫臭い食材でも塩コショウを掛けるとなぜか気にならなくなります。
甲虫類を数年間頂いてきましたが、素揚げ(2度揚げ)に塩コショウを振ったものが一番美味しいです。
右上から時計回りに、ウバタマムシ、コガネムシ、キマワリ2匹、キボシカミキリ2匹、オオゴキブリ3匹です。
ビールでサクサクとスナック感覚で頂きました。
ハナカミキリ、コガネムシ等、その他はバッタ、野草は天ぷら。
ゴマダラカミキリ3匹、センノカミキリ、アトジロサビカミキリ、
コクワガタ、コガネムシ、スジコガネ、サビキコリ、
左側は、バッタ類。
唐揚げ。
唐揚粉を付けても殆ど取れてしまいます・・・が、僅かでも残るのでお勧め。
下側、コアオハナムグリ多数、シロテンハナムグリ1匹、アオドウガネ1匹。
野草はアキノゲシ、バッタはツチイナゴ1匹、トノサマバッタ2匹。
天ぷら。
唐揚げと異なり、衣は取れずに綺麗に揚がります。
今回は小型のコアオハナムグリがメインだったので天ぷらにしましたが、大型の甲虫では噛み切れないかも・・・
小型の甲虫に限っては天ぷらも美味しいです。
シューマイのトッピングに。
キマワリ4匹、オオゴキブリ、ノコギリカミキリです。
予め油でシッカリ炒めてから、シューマイの上に。
某昆虫料理の本に載っていそうな感じですが・・・私の趣味とはちょっと合わないかも・・・とっても、シュール・・・な感じです。
ガーリック炒め。
バッタ類、キマワリ、コガネムシ、マメコガネ、コメツキムシが入ってます。
植物はアキノゲシ。ニンニクは一玉全部使いました。
秘訣は、油は多め、シッカリ炒める事が重要です。
※水分が多かったり、炒めが足りないとグニャっとした食感で噛み切りにくくなります。
これは成功!塩コショウで美味しく頂きました。

バグズ&チップス(Bugs&chips)。
フィッシュ&チップスを・・・だいぶアレンジしてます・・・
サクサクのポテトチップにカリカリのバグ(虫)がアクセント。
ビールに合います。おすすめ。

バグズ&チップスが美味しかったので・・・2020年、再び♪
今回は、ポテチに、コフキコガネ10匹以上、サクラコガネ10匹以上、カナブン1匹の他、キンミズヒキの若葉の天ぷら、ウツボグサの
花穂の天ぷらも一緒に♪
これは見た目良く綺麗&サクサクでビールにあって美味しい♪
串焼き。
ゴマダラカミキリ、アオドウガネと、奥はカタツムリ。
醤油を着けて焼きました。
殻が口の中に残りますが、遠火でジックリ焼けばなんとか食べれます。
非常時にはこれでも十分なご馳走になるでしょう。

煮マメコガネ。
これはふと・・・マメコガネ・・・マメ・・・豆・・・豆料理・・・煮豆!!
急に思い浮かんだのですが、捕ってから思い付いた分けでもなく・・・何日か探し回りました!!
子供の頃は、あちこちに沢山居た記憶が!! 何処へ行ってもいない!! なぜ!?
そんな中、今回やっと、6匹が集まっていたので採取に成功♪ で、早速♪
こんな、ふと思い付いただけの料理・・・何故にそんなに頑張ったかと言うと・・・
今の時点で、この甲虫料理は・・・串焼き以外は全て揚げ物!!
ほんと、揚げ物にしてしまえば間違いないのですが、マメコガネレベルの小ささならば、普通に煮ても食べれるのでは!?
なんておもったからなのです。
・・・長々書いてしまいましたが、結果、普通に美味しく頂く事が出来ました。
※もし、脚(脚の先のツメ)が気になる方は、先に取り除いてしまうと良いでしょう♪

宝石(コガネムシ)パスタ。 勝手に命名♪
コガネムシは予め素揚げでカラッと揚げておきます。
時々訪れるガーリックの食感&風味・・・だけでなく、コガネムシの食感&風味も♪
見た目も綺麗で♪ 美味しく頂けました♪

そうめん。
暑い夏に♪ 食べる時は別々で♪

宝石アイス。
ほんと・・・諏訪湖でバッタアイスなるものが売られていると知り・・・それをあれこれアレンジして、ムカデやスズメバチなどで作って
みました。
今回は、サクラコガネ。
シッカリ素揚げしてから、ソフトクリームに着けました。
見た目良く、殻もサクラコガネならば、硬すぎずサクサク・・・世界唯一のアイスになりました。
