浜のカニ
浜にいるカニで食用になるものはガザミなど沢山います・・・が、ここではもっと小さいものたち・・・
食用とするには小さい&マイナーな浜のカニたち・・・それらをまとめて紹介します。
6月中旬。
生物系(海藻類も含む)の漂着物があると・・・写真の様に巣が集まっている事があります。
6月下旬。若い個体は砂の模様なのです。
巣穴。小型のものは直径1cm程度、大きなものは3cm程にもなります。
巣穴周辺に細かな足跡が沢山あれば居る可能性が高いです。
6月下旬。甲羅の幅3cm程度。
大人になると全く見掛けない・・・掘らないと見つからないのです・・・相当な遠くでもサッと身を隠してしまうようです。
若い頃の砂模様は何故か消えてしまいます。

8月下旬。
何故かどれも薄い黄色になってました。
このピンク色が色っぽく見える♪


9月中旬。朱色の婚姻色になってます。
10月下旬。どこに居るでしょう・・・簡単か・・・
11月上旬。超絶的な保護色。
スナガニ。
恐ろしく早い!! 早すぎて動いている足の残像さえも見えない程・・・
素揚げなどにされて食べられる事もあるようです。
捕り方:
数年、あちこち掘って分かった事♪
まずは掘る穴の選び方・・・
波打ち際から離れた場所は、砂地が乾いてる・・・スナガニも湿気が無いと干からびる・・・と、言う分けか・・・穴が深いです。
肩の深さまで掘ってもダメな事が多いのです・・・これは労多くして功少なし。掘る価値なし!!
波打ち際に近いもの・・・これは波に洗われてない・・・数時間前に掘ったばかりの可能性大!!
そして、スナガニは水中は苦手で、あくまでも陸地に住むカニ・・・スナガニも深く掘り過ぎると、満潮時に水没してしまうので、あまり
深く掘ってないのです。
そんな場所の穴の中で・・・穴の周囲に細かな足跡があれば、さらに居る可能性大!!
次に掘り方:
穴を観察すると分かりますが、完全な垂直には掘ってません。どの方向か、必ず僅かに斜め方向です。掘る時も一直線にそっち方向へ掘る
だけ!!
今回掘った感想・・・どの穴もちょうど肘程の深さに居ました。
これが分かると、直線で掘った時に居なかったら・・・周辺を少しだけ掘ると出て来る事もありました。
居なかったら・・・それ以上掘っても見つからない・・・別の穴にした方が早いです。
つい、忘れてました・・・掘るのはいつも素手で掘ってます。
素手だと硬い部分と穴のあった柔らかい部分が分かり易いうえに、突然出てくるスナガニも傷付けずに捕獲しやすいのです。

出て来た!!
既に穴の底・・・逃げ場無し!!
砂と一緒に持ち帰ると、砂の中で大人しくしてます。
欠点は、重い事! そして・・・当たり前ですが、砂の量に対して潜れるカニも限られる事!!
沢山獲る程、砂も大量に!!
写真は、砂の中のカニの足が2ヵ所ほど見えてますが、完全に埋まっている個体もまだまだ居るのです。
掘ってスナガニを獲った跡・・・
掘る砂の量はこれだけ!! 幅は手のひらほどで、深さは肘程度までで良いのです。

カニと言えば! ハサミで挟まれる!! ・・・そんなイメージかと思いますが♪
ただ、スナガニに関しては・・・写真の様に・・・手のひら全体で包み込むようにすると・・・安心するのか、とても大人しいのです。
素手で穴を掘り、スナガニの感触があったら・・・砂ごと優しく掴んでバケツに入れるだけ♪

こんな目で見つめられると・・・
下拵え:

極々弱火で熱して行き、動かなくなった時点で終了です。
急激に熱すると、ボロボロと手足を自切してしまいます。
砂が着いたまま鍋に投入したので、そこには大量の砂が!!
これは、湯を捨てて鍋に残った砂だけ別途、処理するだけ♪

ざっと洗ったら、フンドシをねじりながら・・・ワタ(糞)を引き抜きます。
もし、切れてしまったら・・・ティッシュを押し当てると、くっ付くので、引き抜けます。
それでも、もし、ダメだったら・・・掻き出すか、諦めるか・・・どっちにする!?
焼きガニ。
カニ風味が弱い・・・で、閃いたのが焼く事!!
中心まで火が通る様にジックリ焼いたら・・・ポン酢を付けて頂きました。
こは香ばしい風味があり、美味しいです♪
鋭い足先は折ってしまった方が安心して食べれます。

素揚げ。
甲羅の幅1cm程度のものと3cm程度の物を素揚げにしてみました。
小型のものはサクサク〜大型の物はガリゴリ・・・甲羅はそれほど厚くないので全く問題なく頂く事ができます・・・ただ・・・風味がと
ても乏しい・・・な
ぜ!?
他の味がジャマしてたかな!? フン出しのために一昼夜置いたり、フンドシを外すと多少は変わったかな!?

唐揚げ。
ひとつ上↑3年前に素揚げして食べた時は、もう一歩・・・美味しい!とは全力で言えない感じだったのです・・・
今回は、その当時の反省も生かして・・・
1、急に熱を加えると手足が取れてしまう甲殻類・・・まずは極弱火で亡くなられるまで火に掛けました。
まだ元気な個体ほど、バッタのように口からゲロを吐きました。
このゲロは恐らく苦いので、元気な状態で持ち帰ったら軽く茹でる事をお勧めします。
2、そして、前回思い付いた、フンドシを取り除く事・・・フンドシの中には、とても濃い茶色のワタ(糞)が詰まってました。
フナムシ同様に、浜に打ち上がった死骸も食べるので、やっぱり、必ず取り除いた方が良いでしょう♪
2020年、今回は上記2点を行なってから、粉が落ちてしまうのを覚悟して唐揚げにしてみました。
結果、思ったよりも唐揚げ粉が残って良い感じ♪ そして・・・いざ、実食!!
写真は、スナガニ5匹の唐揚げと、その下は大量に釣ったイサキの子の唐揚げです。
さてさて♪♪♪
サクサク〜!! 美味い!!
やはり、糞などの異物が邪魔をしてたのでしょう・・・ビールに合うサクサクの食感に以前の記憶よりもハッキリとカニの風味を感じる事
ができました。
これは美味しいです♪ おすすめ♪ 食べる際には、上記、1,2を実行して下さい♪

甘露煮。
風味の弱いスナガニ・・・どうやって食べたら美味しくなるか考えていたら・・・少し前に磯の小ガニ達の飴煮が美味しかったのを思い出
したのです。
味噌汁。
唯一の定番だった素揚げがやや残念だったので、味噌汁も作ってみました。
風味は悪くない・・・カニの風味があります・・・ただ・・・薄い。
これは普通にカニの味噌汁を作る感覚よりも、もっと多くのカニを投入する必要があります。

味噌汁。
今回は炙ってから使いました。
そのまま使うよりも風味がでるので、おすすめです。
・・・でも、期待し過ぎない様に・・・

焼いたスナガニを泡盛へ。
風味があり、そこそこ悪くないです。
これは、雰囲気半分、風味半分で頂きましょう♪
オサガニ。
とても横長で目は長〜い。とても特徴的なカニです。
干潮時に砂浜に取り残されていました。
ガン漬けにされる事もあるようです。

今回は、この1匹しか見つからず・・・しかもメス・・・住んでいた場所から、ヒメヤマトオサガニではなく、ヤマトオサガニとしまし
た。
因みに甲幅は、2.6cmでした。
ヤマトオサガニ。
オサガニに似てますが、ハサミの形が違い、甲羅横の切れ込みが2つです。
良く似たヒメヤマトオサガニも存在します。一番簡単な見分け方は、繁殖期に見られるウェービングと呼ばれる踊り♪
ヤマトオサガニは、ハサミを内側にしたまま持ち上げる・・・両手を胸の前で組んで行なう中国の挨拶のようです。
ヒメヤマトオサガニは、ハサミを完全に持ち上げます・・・日本の万歳♪の形。







ヒメヤマトオサガニ。
両手を上げて万歳する求愛行動(ウェービング)を見たら、この種だと直ぐに分かります。
オサガニ、ヤマトオサガニよりもひと回り小さなオサガニです。
大きなもので、甲幅2.3cm程度でした。

綺麗に洗い、極弱火で茹でて締めたもの。
急激に火に掛けたりすると、手足を切ってしまうので、この様にします。


今回は、一部をガン漬けに。
茹でて身を磨り潰したものに、塩3割程と一味唐辛子を入れて混ぜたら、2〜3ヶ月置いたら完成です。

5ヶ月経過・・・夏場の高温を避けて冷蔵庫に入れていたので、少し長めに熟成させました。
フタを開けたら・・・ぷ〜ん♪ この香り♪ 熟成してる♪ 口の中に唾液がジュワ〜って出て来ました♪
今回は、お酒のあてに・・・熟成したカニの風味が美味しい♪

ごはんに。
塩分が濃いので、この量をあちこちに広げて・・・美味しい♪

パスタに。
アンチョビの様に使う事もできます。
手軽で美味しい♪
1、フライパンにオリーブオイルと、みじんにしたニンニク、ガン漬け、パセリ、唐辛子を入れて炒めます。
2、パスタを茹でたら、1のフライパンに茹で汁少々と一緒に投入!!
3、少し火を入れて混ぜたら器に盛って完成!!
最後に炒ったパン粉を投入して混ぜても美味しいようです。

またまたパスタに。
今回は、和えるだけのパスタのタレ(ゴマ油で炒めた高菜)と一緒に使いました。
塩味濃い目なので、量はお好みで♪ 美味しいです♪

今回採取したもののうち、大きなもの7匹は素揚げに。
干潟なので、泥風味でないか不安でしたが、全く問題なし。
揚げている時にフンドシだけでも取れば良かったと思ったのですが、そのままでも全然大丈夫。
小型なのでサクサクとして心地良く、カニの風味もありました。
2020年11月末。
磯にて・・・山〜磯〜海となっている場所で、磯も山も超硬いチャートで出来ている場所・・・でした。
こんな岩ばかりゴロゴロしている場所に!! なぜここに!? どうやって来た!?



喧嘩して完全にロックしてます。(下のカニが上のカニをロックしてます)


アシハラガニ
河口周辺の砂泥地で葦が生えている所にいました。
良く似た種にヒメアシハラガニがいます。
万葉集に葦蟹(アシガニ)が食用として登場します。
ガン漬けとしてシオマネキの代用として利用される事があったり・・・少し前の日本では、このアシハラガニはメジャーな食材だったと
か。
その他、韓国でも食用にされているようです。

MAXサイズになると、サワガニなどよりずっと大きくなるのですが、逆に食べ難くなると思われ・・・結局、サワガニよりも少し大きめ
程度の個体を採取しました。
捕らえて家に着くまで時間が経ってましたが、綺麗な水道水に1時間程入れて置いたら・・・結構な糞が出てました。
激熱の部屋なので当日頂きましたが、涼しい時期ならば、1日置いた方が良いでしょう♪

素揚げ。
アシハラガニを食べる韓国での食べ方は・・・天ぷら!! とか。
殻のまま衣を付けて!? 翻訳の違いか!?
兎にも角にも・・・天ぷらでは違和感あり過ぎ・・・どちらにしても食べれるのならば、美味しく食べれそうな素揚げで♪
サワガニよりも僅かに大きいサイズで、ボリュームあり、変な味などなく、これは普通に美味しく頂けました♪

ここでひとつ注意!! 美味しく頂けました♪ とか書きながら・・・
潮の干満のある柔らかな干潟・・・この場所で生活するのに、この足先は何!?
他のカニと比べても鋭すぎる足先です!! 口に入れる前に折り取ってしまう事をおすすめします!

唐揚げ。
危険な足先だけ先にバリバリ食べてから、食べて行きました♪
ビールに合って美味しい♪

甘露煮。
まだ少し煮詰め方が足りない気がしますが、これはカニの風味があり、美味しいです。
アシハラガニかヒメアシハラガニか・・・
この写真だけでは、同定するには情報が不足ぎみ・・・
(アシハラガニも砂模様の個体がいるのです。)

全身にポツポツとトゲあり、カニなので当然ハサミもあり・・・素手での捕獲は危険です。
ひっくり返すと・・・ご覧の通り。 この特殊な足でアッと言う間に潜ってしまいます。
甲羅の幅8cmの大型個体。
浜でアオイソメを使った投げ釣りで釣れて来て・・・針を外したら、その場でズリズリと!!
こんなとこでも潜る!!
海岸に出来たタイドプール。
こんな状態になっているのはなかなか見掛けません・・・ふと本でキンセンガニを見掛け、ブタレバーを持って出かけたら偶然目の前に!
まさか居るとも思わ
ず、半ば放置でビーチコーミング。
帰りがけにちょっと寄ってみたら・・・いた!! まさか!!
肉や魚のアラなどを放置すると、どこからともなく集まってくる習性があるのです。
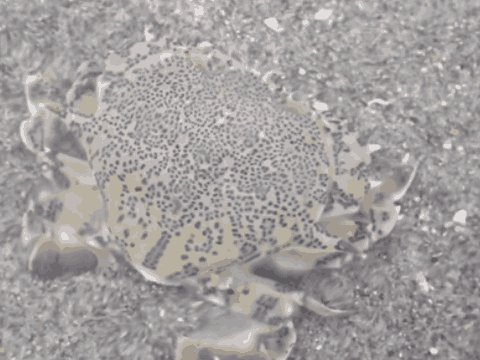
アッと言う間に砂の中へ・・・足の形からも想像できますが、泳ぐのもメチャ速かった!
キンセンガニ。
一番大きかったものは、(両側に飛び出ているトゲを除いて)甲羅の幅が5cmでした。
ここの砂浜に居るとは思いませんでした・・・それもそのはず・・・何度も何度もビーチコーミングしていても全く見た事が無かったので
す・・・それもそのは
ず・・・砂に潜るのがメチャ得意。
捕獲はアミで砂ごと掬うと良いとか・・・私は片手(素手)で探り、もう一方の手に軍手を着けて捕りました。握ると丸まって何故か大人
しくなるのです。
素揚げ。
殻が硬いので素揚げは難ありとの情報だったのですが、試しに小型の物も採取してみました。
大きさはサワガニと同じかやや大きい程度。
ガリッガリッ!! 噛み砕くと自分の頭蓋骨に響いて凄い音! これは厳しい・・・
丸ごと頂けるのは良いですが、やはり難あり。
写真は、1匹だけこちらを向いてます・・・ただのお遊び。
半分は冷蔵庫へ保存し、翌日キッチンペーパーで包んでレンジでチン。
当日より食べやすくなってました。一番硬い甲羅を取り除いて頂くのもありかな!?
塩茹で。
一番大きかったものから2匹を選んで塩茹でにしてみました。
全身の殻がとても硬い上に、甲羅を外すことも出来ない!! メチャ硬い!!
何とか殻を外しましたが、一つ一つの肉が小さい・・・美味しいのですが、とても食べた気がしない・・・
お酒をちびちびやりながら頂くと良いですが、手がベトベト・・・フィンガーボウルがあると良いかも。
味噌汁。
カニ料理の定番!! キンセンガニのおすすめの頂き方です。
風味の良い出汁がでるキンセンガニは、甲羅を途中まで外して使いました。
毎日でも頂きたいです。これほど美味しいのは体が欲する栄養分が含まれているからか・・・

またまた味噌汁・・・ですが、暑い夏は冷製味噌汁。
風味良くサッパリと美味しく頂きました。

2022年10月。浜で投げ釣りをしていたら1匹だけ釣れました。
身を半分に割って作りました。かに風味満載♪
味噌ラーメンに。
甲羅の幅が8cmもある大型のものだったのですが、それでも小さめ・・・味噌汁の出汁にしようと思っていたのですが、晩酌が長引い
て・・・そろそろご飯を食べて寝たい・・・そんな時・・・味噌ラーメンが手元に♪ 同じ味噌ならば♪
クーラーで冷えて仮死状態だったものを、ジックリ茹でた後、殻を外してバラし、味噌ラーメンを作りました。
こんな単純な食べ方ですが、美味しかった♪
甲羅酒。
たまたまこの個体だけ甲羅が薄かったようです・・・
炙っている間にパチパチとヒビが入ってしまいごらんの通り・・・だだ漏れ・・・ですが、
風味は付いて美味しく頂けました。
もっと大きな個体でドバッとやってみたいです。



ソデカラッパ。
今まで水族館でしか見た事がありませんでした。しかも、身近な浜で見られるとはツユほども知らず・・・
目に入って気付いた瞬間、何が起きたのかわからなかったほど・・・
カラッパの仲間は通常食用にはされないとの情報がネット上で沢山見つかりますが、愛知県知多半島で僅かに販売されているとの情報の
他、中国でも食用として販売されているようです。
大きく見える甲羅も実は兜のように側だけ・・・食べれるのは殆どハサミの肉だけのようです。
